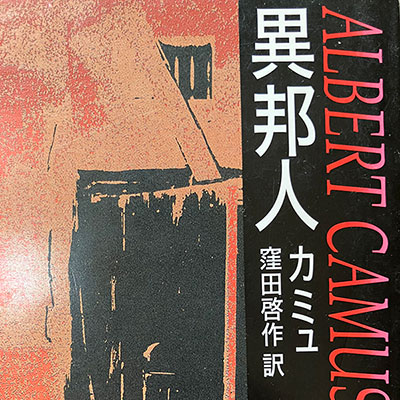
「今日、ママンが死んだ。」
「親の呼び方問題」というのがある。
子供の頃、パパ、ママ、と呼んでいたのに、いつからか恥ずかしくて、呼べなくなる。
お父さん、お母さん、から、「お」を取って、とうさん、かあさん、と言ってみたりする。でも、優等生っぽくてかっこわるい。
「おやじ」「おふくろ」。
友人の前でそう呼んでみたりするが、自分の中で定着しない。親に面と向かって、そう呼ぶのはハードルが高い。「今までそんなふうに呼んでいなかったのに、急におやじって、こいつ、背伸びしてるな」と思われそうだ。
トト、カカ。チチ、ハハ。などの二文字シリーズは、直球でもなくとんがった感じもなく、一見良さそうだ。
だが、やっぱりどこか違う。
前者はやや子供っぽく、後者は会話する時には不自然だ。
「親の呼び方問題」に正解はなく、みんな、どこかで妥協して、折り合いをつけて暮らしている。
「今日、ママンが死んだ。」
フランス人作家アルベール・カミュの代表作「異邦人」。
この作品の、有名な日本語訳の書き出しが、これだ。
「ママン」というのは、秀逸な表現だと思った。
例えば「ママ」だったら、日本人の感覚だとなんとなく甘ったるい感じがして、この作品にはそぐわない。異邦人の主人公ムルソーは、徹底的に乾いていて、母親が死んでも、人を殺しても、とても淡々としている。
ムルソーは「ママ」とも「かあさん」とも「かあちゃん」とも言わない。言うわけがない。
「ママン」で始まったからこそ、その後の話が、不気味で不可解で、それでいて色気のある感じになった。